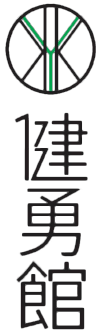笑顔に始まり、笑顔に終わる空手道教室
武道は「礼に始まり、礼に終わる」と言われる武道です。
ですが、健勇館ではその更に前後に笑顔で練習を楽しみにしながら笑顔で道場に来て、練習後に「今日は新しく〇〇ができるようになった!」「なかなか直らなかった〇〇が改善できた!」と笑顔で帰れる道場を目指しています。
松濤館の特徴
競技として空手道をやる場合に、組手には流派はないですが、形は流派の特徴が色濃く出ます。
特に大会や昇段などでは、四大流派という全国的に普及した4つの流派があり、松濤館はその一つです。
特徴としては動きがとにかく大きくダイナミック!で、空手をやっていない人が観ても「カッコイイ!」と思う事間違い無いです。
また、世界中に見ても四大流派の中でも一番普及している流派で、伝統派空手と言ったらこの動き、と言える代表的な動きをする流派です。
ご入会について
ご入会の流れ
まずは見学・体験を最低1回はしていただき、体験後の説明と一緒に入会申込書をお渡しします。
後日申込書に必要事項を記入の上、入会金と一緒にいただきます。
費用について
| 最初にかかる費用 | 入会金 2,000円 初月会費 ツバメ・隼クラス:5,000円、たまごクラス:3,000円 ツバメ・隼クラスはご家族で入会いただくと家族割引が適用となります。 家族2人目が4,000円、3人目以降は3,000円となります。 |
|---|---|
| 道着 | 約10,000〜15,000円 |
| スポーツ保険料(任意加入) | 中学生までは年間800円、高校生以上は年間1,850円 |
ご入会後の流れや昇級・大会について
ご入会後は、まず昇級を目指して頑張りましょう!
入会時は白帯で、級が無い「無級」と言われる状態からスタートします。
帯の色は黄・橙(オレンジ)・緑・紫・茶となっていきます。
黄・橙までは基本と言われる突きと蹴り、緑帯からは形を覚えていくので、徐々に難しくなっていきます。
たくさん練習して一緒に昇級を目指しましょう!
昇級試験について
健勇館では10〜1級まで年3回の昇級試験があります。
練習内容や通う頻度によって昇級回数は個人差がありますが、だいたい年1〜2回、昇級していきます。
昇級には技術の他に「帯を自分で締められる」「道着を自分で畳める」「組手用防具を時間内にキレイに片付ける」などの礼節や、「靴や物の整理」「返事や挨拶」など普段からしっかりと出来ているかなども含めて合否が判断されます。
また、昇級試験を目指して頑張っていく中で「大会に出たい!」と言う子は、まずは市民大会やブロック大会などで出場を目指し練習を重ね、ゆくゆくは県大会に挑んでいきましょう。
大会について
大会は年間で市大会が1回、西毛ブロック大会1回、県大会3〜4回を基本とし、他にもオープン大会をいくつか案内し、参加しています。
出場するメンバーは、基本的に希望者の中から師範の私が決定します。
選手は基本的に形、組手両種目に挑戦する方針ですが、出場枠を超える場合は1種目に絞る事もあります。
空手の効果について
美しい姿勢が身につきます
空手、特に形をする時には姿勢を正してキレイに礼をしなければいけません。
道場の出入り時や練習の初めと終わりに礼をしますが、正座での礼から立ち礼まで何度も礼をするので、自然とキレイな姿勢の習慣が身につきます。
全身が鍛えられます
圧倒的に全身を使う運動なので、体の隅々までコントロールできるようになります。
空手は昔から「下半身の使い方が大事」「背筋で突く」「体の軸を意識する」「上手な人ほど腹圧や体幹を使う」などと言われ、まさに頭の先からつま先まで意識しなければなりません。
また、特に形は基本的に左右対称で作られている物が多いので、他のスポーツでありがちな片方だけの動きになりづらく、全身をバランスよく鍛える事ができます。
「技」と「心」が磨かれます
空手には形と組手の2つの競技があり、それぞれに違った目的があります。
形とは、決まった一連の動き(攻撃・防御・体の動かし方)を一人で行う稽古法です。
決められた形を何度も何度も練習し、職人が技術を高めるように積み重ねていきます。
正しい姿勢・呼吸・重心の使い方を身につけ、一つひとつの技を正確かつ美しく行い、戦いの「想定相手」を意識し、集中力・精神力を養います。
組手は、何度も技の練習をするのは同じですが、「相手がこう動いたら自分はこう動く」や「相手の裏をかくために自分はこうする」など、事前にあらゆるシミュレーションとその状況に合わせた対人稽古・試合のことです。
攻防の流れの中で技を応用的に使い、実戦感覚や判断力を鍛え、礼節や勝ち負けに対する精神性を学びます。
空手を習うと形の「技」と組手の「心」の2つを同時に磨くことができます。
運動能力のすべてが習得できます
空手に必要とさせれる能力は多種多様です。
筋力、筋持久力、瞬発力、全身持久力、敏捷性、バランス能力、コーディネーション能力、反応能力、変換能力、連結能力、定位能力、巧緻性など、一般的に運動で必要とされる能力はほぼすべて必要なので、偏る事なく習得できます。